第19回 会津歴史探訪の旅
斗南に移封になった旧会津藩士の足跡を訪ねる旅


まず斗南藩についてであるが、明治2年11月、松平家の再興が許され、松平容保の嗣子である生後5か月の容大(かたはる)公を藩主に斗南藩が立藩された。3万石と減っただけでなく実際の米は7380石、金品入れてわずか1万石と言われる。斗南藩領地は斗南半島と三戸や五戸近郷との飛び地である。明治3年4月には黒羽藩から引継ぎが行われ、移住第一陣300人が明治3年4月29日に品川沖から蒸気船で八戸港に入り翌日には五戸に藩庁が置かれた。明治3年の先発の藩士達がむつ市田名部に着いたときは住民の提灯行列に迎えられたという。五戸の仮藩庁は明治4年2月にはむつ市に移った。御薬園で生まれた幼い藩主容大が明治3年9月に駕籠に収まり会津を出立、仮藩庁の五戸まで20日間、明治4年2月、円通寺にたどり着くまで五戸からさらに3、4日かかったとみられる。容大公の為、牛の帯同で新鮮な牛乳付きだったという。陸奥の円通寺の藩庁職員は山川浩大参事を含めて約118人で組織され容大公を迎え藩士たちの士気も上がったという。新潟から陸奥湾に明治3年6月に蒸気船で上陸した藩士家族は1800人と言われる。他のルートも含め総勢17,300人2800戸の藩士家族が移住した。しかし明治4年7月に廃藩置県が断行され立藩からわずか1年9か月の斗南藩であった。艱難辛苦、想像もできない悲しみと憎しみが交錯したことだろう。その間は耕作に適さない不毛の地で慣れない開墾で食糧不足で木の根や犬の肉をも食したという。さらに下北特有の猛烈な冬の嵐で押しつぶされ命を落とした家族も多い。廃藩置県の断行によって、藩主御一行は明治4年8月25日早朝、藩庁の円通寺を出立東京へ向かった。会津や仙台や東京に戻ったり、平民になったり、帰農したり、商人になったり、斗南を離れた人は8000人を超えたという。斗南に残った藩士家族は約50戸であったという。現在も末裔は誇り高く居住されている。時代に翻弄された会津藩士の人生は無念そのもの苦労の連続だったことは想像に難くない。
初日11時過ぎに最初の訪問地、三戸市の浄土宗『観福寺』に到着した。三戸移住の旧会津藩士大竹秀蔵が明治4年に『白虎隊供養碑』を建立した。明治14年頃の飯盛山より早い最初の碑であった。白虎隊士17名の名前が刻まれた碑に焼香したあと、住職が自ら説明してくださった。大変な生活を強いられた会津藩士に同じ日本人の同胞ではないかとの地元の声もあがっていたそうである。
さて、『観福寺』からは住宅街の細道を通り、12時に『悟真寺』につき『旧会津藩殉難者招魂碑』を見学、題字は松平容大、文は南摩綱紀(東京高等師範学校教授)と渡部(逓)次郎(三代目三戸小学校校長)である。『悟真寺』には会津藩家老の萱野権兵衛を慕う会津藩士によって位牌が安置されていた。権兵衛は新政府による制裁で主君をかばい会津藩の親戚である飯野藩保科家下屋敷で介錯自刃した。墓は白金の興禅寺と若松の天寧寺にある。
次に隣の『三戸大神宮』を訪ねた。十九代山崎宮司による個人経営で自由度を維持しているそうである。キャラクターにもなっている『みこ(三戸・巫女)にゃん』が11匹いるそうである。昔は蚕を狙う鼠を退治したそうである。ステンドグラスを多用し明治モダンの香りがする珍しい神社であった。TV『八重の桜』以降、他県からの旅行者も増えたそうである。ここには三戸へ移った日新館館長の杉原凱先生の墓を弟子達が境内に建立している。藩士は横迎町(むつ市)の立花屋文左衛門氏の倉庫を借り受け日新館を開校。遠隔の地には分局を設けて子弟の教育に力を入れた。町家にも勉学を呼びかけたことは特筆すべきであった。このようにして移住した会津藩士は日新館を軸として教育界に多大なる功績を残したのである。ここには会津藩士達を祀った墓所や無縁仏もある。
その後、昼食は八戸プラザホテルで市街を眼下に望みながら『せんべい汁定食』を楽しんだ。ホテルの会長によれば斗南藩士の神田小四郎の長男、神田重雄は八戸市初代議長を経て市長2代から4代までを歴任し、八戸漁港の近大化に尽力したという。会津藩士が移った八戸の舘鼻公園に銅像となっている。娘子隊で殉節の中野竹子の妹中野優子の墓もあるそうだ。会津からの我々はこの旧領地でも日野や松坂同様、時を越え歓迎されている事を実感した。
北上して三沢市『斗南藩記念観光村・先人館』で参加されていた宮城会津会の赤塚吉雄(高15回)氏に案内をしていただいた。ここに牧場を開墾した会津藩下級武士の廣澤安任は日新館から御茶ノ水昌平学を卒業して容保京都守護職の先回り調査を担っていた。後に新政府から大伝馬町牢屋に投獄になり、アーネスト佐藤が嘆願して救われた。その後廣澤が新宿角筈で日本で初めて牛乳を売るまでの牧場開墾の歴史、大久保利通が新政府への誘いに廣澤に会いに来た部屋の間、さらに長崎のような国際貿易港を陸奥湾大湊に開港するためこの三沢の辺りの太平洋から陸奥湾に通じる半島を横断する運河を掘る一大計画を示す地図が展示されていた。残念ながら予算不足の為計画で終わった。これが完工されていたら青森県が国際貿易港としてどう発展していたか、想像するだけで胸が躍る。
むつグランドホテルで開かれた夜の交流懇親会には斗南會津会の山本相談役、遠藤会長、坂本副会長、遠島事務局長の方々の参加で楽しい交流時間を共有できた。ご案内いただく訪問地に関する情報やむつ市作成の斗南藩の冊子、下北哀史のCDなどの資料をいただいた。
翌日は藩庁跡曹洞宗『円通寺』にて公務ご多用中の山本市長のご挨拶をいただいた。来年2024年は斗南藩155周年、むつ市と会津若松市の姉妹都市締結40周年を祝う行事が行われるそうである。様々な毎年の相互交流が長年に渡り続いている。円通寺の境内には会津藩士招魂碑がある、碑面は容大公の揮ごうで碑文は会津藩士南摩綱紀博士の撰による。容保は謹慎の身であったが明治4年3月斗南藩に鞍替えとなり函館、佐井を経て容大が待つ円通寺に7月に到着、親子初対面であったといわれ、廃藩置県で上京命令が出るまで親子水入らずの1か月を過ごした。斗南が丘として市街地が建設計画されていたが夢に終わった。会津人の先見の明と一徹なまでの姿勢は物心両面で残した功績は大きいと言われている。
隣の真宗大谷派『徳玄寺』は肉食妻帯と緩く、容大の遊び場になっていたという。重臣の会議場でもあった。ここにも萱野権兵衛を偲んで位牌が安置されている。広い墓地があり境内には51本の作品を残した名監督、地元生まれの川島雄三映画監督の墓がある。
斗南藩士となった会津藩士が上陸した記念碑を訪ねた。明治3年、新潟から海路で新政府借り上げのアメリカ蒸気船ヤンシー号に乗りここ大湊に上陸した。石碑は鶴ヶ城の石垣に使用されている慶山石を用い会津若松市を向いて建てられている。碑文の揮ごうは会津松平家第13代当主松平保定氏による。むつ市の「む」と「會」の字を両脇に堀り、むつの「ハマナス」と会津の「赤松」の植栽に囲まれている。ここまで斗南會津会の坂本副会長、遠島事務局長にご案内をただいた。
一路本州最北端の大間崎まで移動、津軽海峡の18キロ先には函館汐首岬を望む。一本釣りされた440キロのマグロのモニュメントは圧倒的な存在感がある。
ランチは長宝丸で分厚いマグロ丼をいただいた。店長の説明では釣り船は1億円を越えるそうである。若い漁師が満月の日に夜通し群れの先頭をソナーで狙う。小魚の盛り上がりもあり、群れの匂いがするそうだ。
大間町にある私設会津斗南藩資料館『向陽処』の館長で説明いただいた木村重忠氏は容保が京都守護職任命の際、随行した会津藩士木村重孝の曾孫に当たり4代目末裔で、元斗南会津会会長も務められた。斗南藩が飛び地になっているのは南部藩が会津藩の味方をした罰で取り上げられ斗南藩になったそうである。なんとも申し訳ない。貴重な資料の一つで容保公がこの地を去るにあたり容大公の御名で布告を出され、実物が展示されている。大意としては『東京に召喚され皆と苦労をともにできないのは耐え難いが、これまで幼齢でありながら重職を奉じることができたのは皆が苦難に耐え奮励したおかげだと喜んでいる。この先も身を削り心配いただいた天皇の限りない恩に報いることが私の望みである』と藩士に詫び、天皇を仰ぐ書翰である。また木村館長によると竜馬暗殺は江戸幕府の組織である京都見廻組によるものという説があるが佐々木只三郎説もあるとのこと。また容大公の陸路移動に牛を連れていた話も木村館長による。この後、霊場恐山を見学して八戸に戻った。
3日目には十和田市『澄月寺』を訪ねた。ここには戊辰戦争戦死者招魂碑があり、大義に殉じた家老や重臣、白虎隊員も含む約3000人を供養するものである。旧藩主容保による「今もなほしたう心は変わらねど,はたとせあまり世は過ぎにけり」の歌が刻まれている。
その後、青森市の『ねぶたの家ワ・ラッセ』でねぶたの実物に触れ、三角形が印象的な「青森県観光物産館アスパム」で食事、お土産を求め、その後、世界遺産である「三内丸山遺跡」を訪ねた。6500年前の縄文最大級の遺跡である。縄文早期の遺跡は東北に多いそうである。すでに栗の木の栽培をしており、クルミ、ウサギ、シカ、イノシシ、クマの骨が水没して残り、魚の骨、アサリ、ハマグリ、シジミなどの海の物も残っている。ごみの廃棄日が定められ社会性が見られる。墓もまとめて作られ病気感染を防いでいた。
新青森駅から16時17分発の新幹線に乗り帰路に就いた。斗南藩主・斗南藩士の足跡の詳しい事実が分かり、今も会津との絆が強い斗南の旅であった。
斉藤 仁(高20回)
第18回 会津歴史探訪の旅
蒲生氏郷の足跡を訪ねる旅


お昼は大平副会長などのご挨拶で旅の安全を誓いつつ、日野名物の「鯛そうめん御膳」をいただいた。鯛の身がのって、鯛を甘辛く煮た汁でソーメンを炊くそうである。お祭りの時に欠かせないという晴れのご馳走に舌鼓を打った。地元ガイドさん2名と合流し、2班に分かれここから日野町をご案内いただいた。
まずバスで、「蒲生氏郷公像」を訪ねた。蒲生氏郷は日野の中野城で1556年蒲生賢秀の子として生まれ、13歳で織田信長の岐阜城へ人質に出された。氏郷は信長に見込まれ、信長は娘冬姫と結婚させ日野に帰らせた。1582年、本能寺の変で信長が明智光秀に討たれると氏郷は信長の家族を日野の中野城にかくまった。室町時代には日野は蒲生氏の城下町として大きな変貌をとげ、歴史の表舞台に登場するようになった。町の繁栄の基礎を築いた蒲生氏は400年以上この地を治め、商工業の保護・育成に努力し、鉄砲や鞍などを特産品として生み出した。今も日野の人々の心に生きているのが若くして戦国武将の器量を備えていた文武両道の蒲生氏郷公である。信長亡き後に豊臣秀吉に付いた氏郷は楽市楽座を開き、産業振興に優れた力を注いだ。江戸時代に漆器や薬売りの行商で有名になった「近江商人」の基礎をこの時代から作っていた。その後伊勢平定に功を上げ秀吉の命により南伊勢の松ヶ島12万石をもらい移封した。日野の若松の森にちなんで松を、秀吉の大坂(明治元年に大阪に変更)から坂を取り「松坂」と名付けた。日野からも商人が移った。その後、氏郷は1590年秀吉の小田原城攻めに功を立て、伊達政宗の領地であった「会津黒川」92万石をもらい、日野の若松の森にちなんで今の「会津若松」と名付け、領主となった。新しく築城し、幼名の「鶴千代」にちなんで「鶴ヶ城」と命名した。城下町の整備、産業の育成発展、上方の文化を導入した。会津塗も日野椀の漆器職人を招いて技術導入されたものであり、漆器の風情がどこか似ている。会津は関東の徳川、中国の毛利に次ぐ天下三番目の領地であった。
ここからまたバスで「馬見岡綿向神社」(うまみおかわたむきじんじゃ)へと向かった。神社は豪壮な作りであり蒲生家の氏神として信仰を集めている。毎年、5月初めに行われる湖東最大の日野祭りでは絢爛豪華な曳山でにぎわうという。その参道を覆っていたのが氏郷が故郷を偲んで懐かしんだという「若松の森」である。
ここから「中野城(日野城)」へ向かった。蒲生定秀が当主の1533年から築城され、鎌倉時代の初期から約400年間続く蒲生家6万石の最後の本城であった。貞秀の孫の氏郷は西側の荒野に西大路の町割りを作った。城跡には本丸跡や掘割などが残されており、産湯跡や氏郷と冬姫の紹介看板を見学した。氏郷が伊勢松ヶ島を与えられると日野の繁栄の幕は閉じた。
そこから、奈良時代から蒲生氏の菩提寺である浄土宗の「信楽院(しんぎょういん)」に向かった。信楽院本堂の天井画は竜が荒れ狂う様の水墨画であり、その「雲竜」は壮大で豪快であった。
そこから城下町の風情を残す静かな「清水町」を歩いて、小さな地蔵堂の下にある由緒ある「若草清水」に着いた。氏郷が茶の湯としてこの水を使ったという。土手は曼殊沙華が満開で華やかさを添えていた。通りすがりに、旗を目にしてか「会津からですか、ようこそ」と、日野は会津びいきで、とても親しげに声をかけてくださったので一気にこの町に親近感がわいたのであった。
そこを抜けると「歴史民俗資料館・近江商人館」に着いた。日野は近江商人のふるさとである。もとは日野商人の一人である山中兵右衛門の豪邸自宅である。「八幡表に日野裏」と言われたように豪商でありながら家の表側は富を誇示するのでもなく質素・倹約を美学としたつましい生活態度をあらわしている。館内には日野商人の薬(萬病感應丸)や漆器日野椀などの行商品、道中具、家訓、外国産薬石、日本最古の120年前の牛久ワインなどが多数展示されている。室内の桟も角をとり、四方柾目の柱、屋久杉天井、引き手は七宝焼き、廊下は松一枚もの、いたる所に拘りが見られた。「近江日野商人」400年の歴史を表す家訓の「慎み」十カ条、売り手、買い手、世間よしの「三方よし」の商業道徳が感じられる。日野商人は会津への途中の埼玉、群馬、栃木などの北関東を中心に須賀川まで「持ち下り」と言う酒・醤油などの行商をし、チェーン店である400店を超える多くの出店や特約店を設けた。商人仲間の団体も結成し、物流の定期便伊勢飛脚などロジスティクスを構築しており、また収穫時払いなど掛け売りをして融通を付けていたそうである。現代のビジネスの基本はできていた。旦那が出張続きのため主婦は「関東ごけ」と呼ばれたそうである。「近江商人」は総称であり、地域ごとにそれぞれの特徴を持つ。「八幡商人」や「五箇荘商人」は江戸などの大都市で店を拡充するデパート型で伊藤忠、丸紅、ワコールなど多数の現代企業の原点である。「高島商人」は日本橋高島屋を代表に、南部藩の勧誘で岩手に商人の集団移住、「日野商人」は地方都市や農村で小さな支店(出店)を多店舗展開するチェーンストア型で関東経済圏で商機をつかんだ。道中には契約の旅籠も沢山あり、情報交換のみならず、関東の文化や物資も導入していた。にぎやかでテンポの速い「関東ばやし」を祭りに取入れたり、商いで得た富で故郷日野町の神社や16基の曳山など町の振興に隠匿善事で力を注いだという。ここでは興味深く楽しく近江商人を学ぶことができた。
さらに、会津まつりでは毎年日野の祭囃子が甲冑行列の先頭であるという。改めて注意して聞いてみたいものである。ちなみに、蒲生氏郷公のお墓は京都大徳寺にあり、会津若松市栄町興徳寺にも分骨したお墓がある。このように会津と氏郷のつながりは長く深いのである。
夕方5時、バスは日野を出発、名古屋のホテルに6時過ぎに到着、7時から「在京と中部同窓会交流懇親会」が開催された。在京大越会長や中部同窓会の小林会長や萱野会女会長をはじめ多数のご挨拶をいただいて、各テーブルに中部同窓会のメンバーが加わって、盛大に開催された。寺木先生の健康の秘訣も披露され驚かされた。さらに会場でも会津の基盤を作った蒲生氏郷の故郷を訪れることができて感無量との声も聞こえた。初参加者も全員で近況や思い出も語たり楽しいひと時を過ごした。
翌日は東海道唯一の海路「七里の渡し跡」を訪ねた。宮宿(名古屋市熱田区)から桑名宿(三重県)までの七里を結ぶ船便で、4~6時間かかったという。木曽三川(木曽川、長良川、揖斐川)を避けるためであった。大名の御座船から庶民用の帆掛け船まで、大きい船は一回に40~50人くらいは運んだという。馬や物資なども運ばれた。すでに鎌倉・室町時代から利用されていた重要な交通インフラであった。天候が悪い時や船に弱い人のために陸路の佐屋街道も用意されていた。
この後は桑名市に移動し「桑名七里の渡し跡」を訪ねた。海上の名城と謡われた桑名城のシンボル「蟠龍櫓」(ばんりゅうやぐら)に向かった。七里の渡しに入ってくる船の監視などの役割を果たしていた。
1591年、秀吉の家臣である一柳右近が桑名に入り、その4年後に伊勢神戸城の天守閣を移築して、揖斐川沿いに桑名城を築いた。これが桑名城の原型になり、1601年、本多忠勝は桑名藩に入封直後、10年をかけて築城した。後に松平氏の居城になった。扇形の一片を持ち扇城と呼ばれ、中国の扇を表す九華から、城址公園を元藩士が九華公園と命名した。九華を「くはな」と読むこともあった。
この後、名物の蛤料理屋が並ぶ城下町を歩き、柿安本店前を通り、「本多忠勝像」を見ながら、九華公園(城址)に入った。中の「鎮国守国神社」はもともと白河小峰城内に松平定綱(鎮国公)定信(守国公)を祀っていたが、国替えで神社も桑名に移った。定信は8代将軍吉宗の7男として生まれ、白河の松平久松家に養子に出ていたが、定信の意向もあり最終的に幕府の命令による国替えで松平久松家のもともとの桑名藩主に戻ったのである。このようにこの神社は幕末の桑名藩の変遷を見守ってきた。桑名城は1701年焼失し再建されなかったが、その後、明治20年に建立された「戊辰殉難招魂碑」(天守閣跡)を見て城址を後にした。
次に向かったのは「十念寺、森陳明(つらあき)の墓」で桑名藩士、新選組隊士であった。陳明は幕末の藩主松平定敬(さだあき)が京都所司代の時、秘書役となって仕えた。上野では新政府への抗戦、定敬と仙台で合流した後、最後は函館五稜郭で戦った。戦後新政府から桑名藩の戦争責任者の差し出し命令に、藩を代表して東京深川の藩邸で切腹した。深川の桑名藩の菩提寺である霊厳寺にも墓がある。
これで幕末の盟友藩である桑名を後にして、松阪に向かった。昼食は松阪牛の専門店「まるよし」で名物の柔らかい牛鍋を堪能した。
その後、まずは丘陵となっている「松坂城跡」(平山城・日本百名城・国指定史跡)である。氏郷は1588年の移封からわずか3年で完成させた。松阪市歴史民俗資料館を訪ね氏郷公の画像や松阪木綿や小津安二郎記念展示などを見学した。現存する建物はないが、豪壮な石垣は往時を偲ばせる。「穴太衆」と呼ばれる専門の職人により、古墳の石棺なども混じった自然石を利用した野面積(のずらつみ)が見どころとなっている。周囲には堅固な石垣を巡らせている点が全国でも屈指とされる。明治22年に「松坂」から「松阪」(まつさか)に変更になり読み方も「まつさか」に統一された。
三の丸に向かうと松坂城を警護する「松坂御城番」という紀州藩の武士20人とその家族が住んでいた「御城番屋敷」がある。美しく刈り込まれた槇垣を巡らせ、今も子孫が住まわれて維持管理をされているのは驚きであった。江戸時代からの最大規模の貴重な現存建造物群として国指定重要文化財となっている。通りの両側に10軒ずつきれいに並んでいる。その一軒は市が借り受けて復元し一般公開している。
この後はお城の高い石垣の外を巡り、豪商「丹波屋」を屋号とする「旧長谷川次郎兵衛家」本宅に向かった。内部は豪商の贅を尽くした部屋で文化財や商材が並んでいる。伊勢商人の中でも一早く進出し、江戸のファッションストリートであった大伝馬町に5軒を持つ木綿商となった。広重の「東都大伝馬街繁栄の図」に長谷川家の江戸店が何軒か描かれている。
最後に「豪商のまち松阪観光交流センター」で買い物をして帰路に着いた。松阪も会津の旗にはすぐに気付いて暖かく話しかけていただいた。ここも会津びいきであり、氏郷の功績を知らされた密度の濃い心地よい旅であった。
齋藤仁(高20回)
第15回会津歴史探訪の旅
戊辰戦争・会津戦争後の会津藩士が 北海道に残した足跡を訪ねる 6月8日(土)~10日(月)の2泊3日・総数37名の参加で会津歴史探訪の旅が催行された。今回も直木賞受賞作家で会津の歴史を中心に時代小説の著作が多い中村彰彦先生が令夫人と同行され、随所で歴史談話を拝聴することができた。
◆初日
 【一日目】
羽田空港を離陸し新千歳空港経由で余市町「ホテル水明閣」に到着。余市町長他8名の出迎えを受けた。
昼食を兼ねた交流会では大越康弘会長、齊藤啓輔町長挨拶の後、北海道余市町福島県人会会長の水野隆志氏の乾杯の音頭に続いて懇親会に入り、中村彰彦先生からも挨拶があり楽しい交流会を持つことができた。
その後ニッカウヰスキー余市蒸留所に向かった。ここは竹鶴政孝がリンゴジュースの販売を支えとしながらウィスキーづくりを成功に導いたところで、連続テレビ小説「マッサン」の舞台にもなった。
次の訪問地からは吉田観光農園社長・吉田浩一氏(会津人子孫)の案内で、蒸留所近くの開村記念碑(旧会津藩士・宗川熊四郎茂友らが、余市に入植して50年目の大正9年、旧藩士及び末裔たちが建立)、黒川の余市日進館跡にある萱野権兵衛殉節碑(旧藩士末孫が昭和12年に建立した慰霊碑)を訪れた。
次は吉田観光農園へ。「余市りんご」は、余市に入植した旧会津藩士たちが苦難の末に栽培に成功した日本初の「緋の衣」が始まりである。「緋の衣」の原木は、吉田観光農園が今日まで守り続けている。余市町最後の訪問は会津藩士之墓碑。余市山田に入植した会津藩の刀匠・七代目鈴木半兵衛香兼友が開拓創業の苦しみを子々孫々に伝えるため、明治21年余市美園の墓地内に「志業永伝」の篆額を銅板に刻み、石柱にはめ込んだ慰霊碑を建立したが、盗難に遭い石柱だけが残ったので、59年に余市在住の会津藩士会が慰霊碑の空碑に「会津藩士之墓」と刻み修復したものである。竹鶴政孝・リタの墓を見学後、小樽市の「ホテルオーセント」へ向かった。夕食を兼ねた会中・会高北海道同窓会間部賢司会長他8名参加の懇親会で、両会長の挨拶の後、参加者一同交流の輪を広めた。
【一日目】
羽田空港を離陸し新千歳空港経由で余市町「ホテル水明閣」に到着。余市町長他8名の出迎えを受けた。
昼食を兼ねた交流会では大越康弘会長、齊藤啓輔町長挨拶の後、北海道余市町福島県人会会長の水野隆志氏の乾杯の音頭に続いて懇親会に入り、中村彰彦先生からも挨拶があり楽しい交流会を持つことができた。
その後ニッカウヰスキー余市蒸留所に向かった。ここは竹鶴政孝がリンゴジュースの販売を支えとしながらウィスキーづくりを成功に導いたところで、連続テレビ小説「マッサン」の舞台にもなった。
次の訪問地からは吉田観光農園社長・吉田浩一氏(会津人子孫)の案内で、蒸留所近くの開村記念碑(旧会津藩士・宗川熊四郎茂友らが、余市に入植して50年目の大正9年、旧藩士及び末裔たちが建立)、黒川の余市日進館跡にある萱野権兵衛殉節碑(旧藩士末孫が昭和12年に建立した慰霊碑)を訪れた。
次は吉田観光農園へ。「余市りんご」は、余市に入植した旧会津藩士たちが苦難の末に栽培に成功した日本初の「緋の衣」が始まりである。「緋の衣」の原木は、吉田観光農園が今日まで守り続けている。余市町最後の訪問は会津藩士之墓碑。余市山田に入植した会津藩の刀匠・七代目鈴木半兵衛香兼友が開拓創業の苦しみを子々孫々に伝えるため、明治21年余市美園の墓地内に「志業永伝」の篆額を銅板に刻み、石柱にはめ込んだ慰霊碑を建立したが、盗難に遭い石柱だけが残ったので、59年に余市在住の会津藩士会が慰霊碑の空碑に「会津藩士之墓」と刻み修復したものである。竹鶴政孝・リタの墓を見学後、小樽市の「ホテルオーセント」へ向かった。夕食を兼ねた会中・会高北海道同窓会間部賢司会長他8名参加の懇親会で、両会長の挨拶の後、参加者一同交流の輪を広めた。
◆二日目
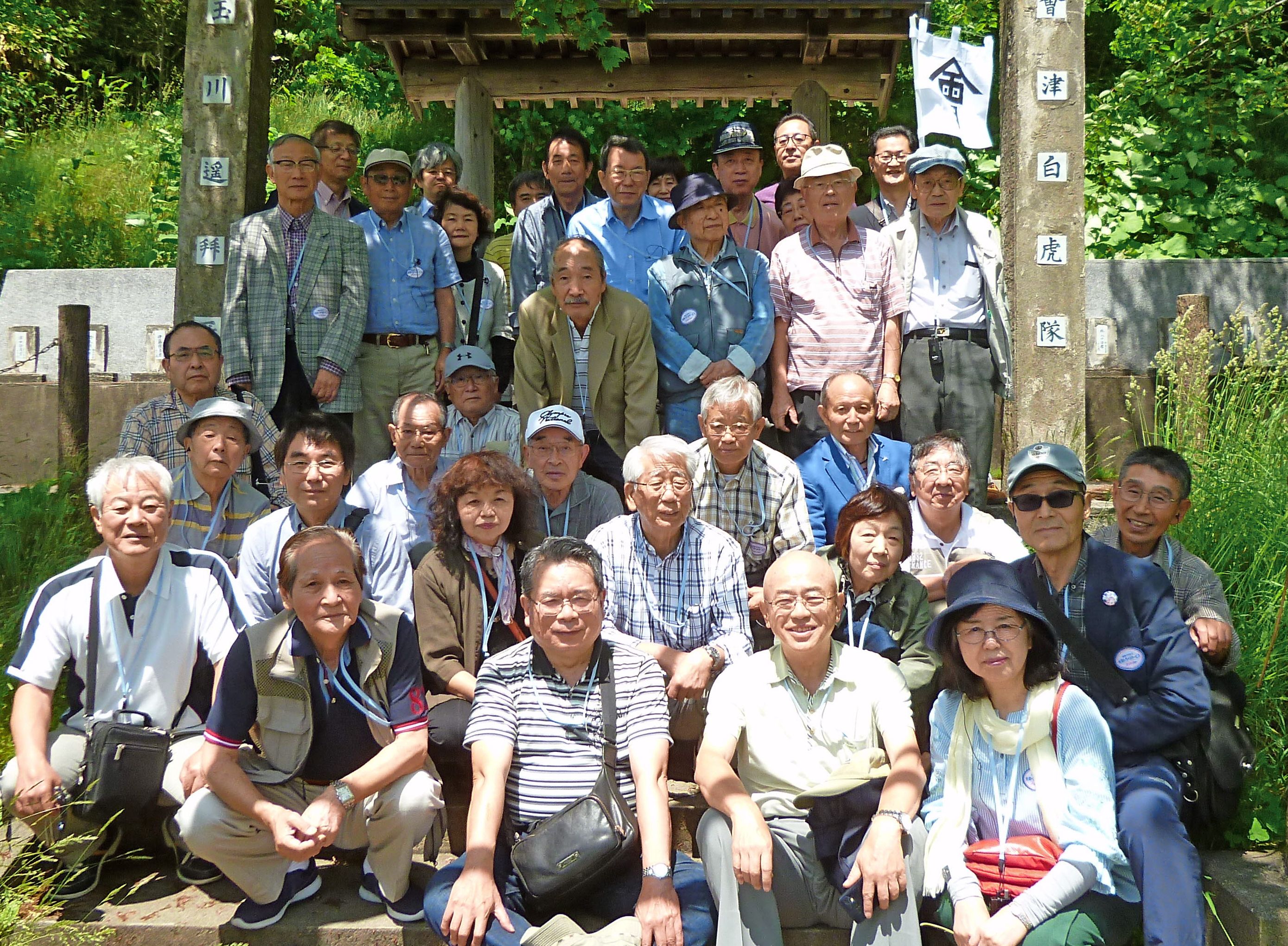 【二日目】
今日最初の訪問地、丹羽地区会津白虎隊玉川遥拝所は発見するのに苦労した。1m超の自生の草を踏み倒して50mほど進み、ようやく辿り着けた。丹羽地区の開拓功労者で会津藩士・丹羽五郎が、飯盛山の白虎隊士19名の霊を祀っている如く、この地にものおもいで大正13年7月建立した。入口にあった大理石に刻まれた漢詩「白虎隊」を吟じ、線香を手向けて会津の地に思いを馳せながら参拝。「温泉ホテルきたひやま」での昼食後、若松開拓記念碑がある若松山法覚寺へ向かう。吉武住職より碑の説明があった。
明治21年の磐梯山噴火で打撃を受けた会津の材木商有志が、豊富な原生林を求めてこの地に入植した。碑は会津で造られ、昭和9年5月に建立された。
次の会津藩遊撃隊上陸の地は森町の内浦湾「鷲ノ木」地区にある。会津藩士は仙台で遊撃隊を結成して榎本軍に加わり、明治元年10月20日、ここに上陸した。2日目の最後の訪問地、土方歳三最期の地碑がある函館市一本木へ向かった。明治2年5月11日の新政府軍総攻撃の日、包囲された弁天岬台場を奪回するために、土方は少数の精鋭を率いて一本木関門に屯する適地に乗り込み、銃弾をあびて戦死したといわれている。
【二日目】
今日最初の訪問地、丹羽地区会津白虎隊玉川遥拝所は発見するのに苦労した。1m超の自生の草を踏み倒して50mほど進み、ようやく辿り着けた。丹羽地区の開拓功労者で会津藩士・丹羽五郎が、飯盛山の白虎隊士19名の霊を祀っている如く、この地にものおもいで大正13年7月建立した。入口にあった大理石に刻まれた漢詩「白虎隊」を吟じ、線香を手向けて会津の地に思いを馳せながら参拝。「温泉ホテルきたひやま」での昼食後、若松開拓記念碑がある若松山法覚寺へ向かう。吉武住職より碑の説明があった。
明治21年の磐梯山噴火で打撃を受けた会津の材木商有志が、豊富な原生林を求めてこの地に入植した。碑は会津で造られ、昭和9年5月に建立された。
次の会津藩遊撃隊上陸の地は森町の内浦湾「鷲ノ木」地区にある。会津藩士は仙台で遊撃隊を結成して榎本軍に加わり、明治元年10月20日、ここに上陸した。2日目の最後の訪問地、土方歳三最期の地碑がある函館市一本木へ向かった。明治2年5月11日の新政府軍総攻撃の日、包囲された弁天岬台場を奪回するために、土方は少数の精鋭を率いて一本木関門に屯する適地に乗り込み、銃弾をあびて戦死したといわれている。
◆三日目
【三日目】
碧血碑は箱館戦争で戦死した土方歳三ら約800名の旧幕府軍戦死者を祀るため、明治8年谷地頭町函館山山麓に建立された。碑名も建立者も不明だが、榎本武揚や大鳥圭介であろうと言われている。碧血とは「義に殉じて流した武人の血は3年経つと碧色になる」との中国の故事によるものである。次は高龍寺にある傷心惨目の碑。会津藩士の箱館病院分院として高龍寺を使用していたが、明治2年5月11日新政府軍が乱入し、負傷して抵抗できない傷病兵13名をメッタ切りにして寺に放火、生きながら焼き殺された。明治13年、惨殺された会津藩士の霊を供養するため旧会津藩有志が建立。碑の前に線香を手向けて合掌した。徳川藩士戦死之霊碑はすぐ近くの実行寺境内にあり、会津藩士・沢田光長が榎本軍80余名を供養するために建立した慰霊碑である。続いての会津ルスイ跡は会津藩が東蝦夷地の領有・警護時代に分営地として建てたが現在は何も残っていないので車窓眺望とした。
次は函館港にある新島襄海外渡航の地碑に立ち寄り、函館朝市「栄屋食堂よさこい」へ。最後の訪問地である五稜郭は我が国最初の西洋式城塞である。大政奉還を経て明治新政府へ引き継がれるまで、蝦夷地における政治的中心地として重要な役割を果たしたが、榎本武揚率いる旧幕府脱走軍により占拠され、箱館戦争の舞台となった。大正に入って「五稜郭公園」として一般開放され、「五稜郭跡」の名称で特別史跡として国の指定を受けている。中村先生の函館戦争の解説を受けながら、復元された函館奉行所を通り、五稜郭タワー展望台から、五角形の五稜郭を始め360度の眺望を楽しんだ。
来年以降の訪問先と中村先生の同行を改めて依頼することを確認して、新函館北斗駅から北海道新幹線で帰路についた。
鈴木忠正(高15回)
第14回会津歴史探訪の旅
6月2日~3日に「会津藩祖・保科正之公の表舞台第一歩の地・山形と会津戊辰戦争の戦跡をたどる」 として歴史探訪の旅が催行された。参加者総数36名。今回も直木賞受賞作家で歴史小説家の中村彰彦先生が令夫人と共に 同行され、随所で歴史談話を拝聴できた。
◆初日
 ▼初日 東京駅発午前8時8分の東北新幹線で山形駅へ。まず山形城跡(霞城公園)。この城は慶長5年(1600)の長谷堂城の戦いの折、城郭が霞で見えなかったことが「霞城」命名の所以。保科正之公が信州高遠から栄転入部したのは寛永13年(1636)、26歳のときである。二ノ丸東大手門や旧済生館本館を見学後「香味庵まるはち」で朴葉味噌焼き御膳で昼食。昼食後寒河江市に向かい、途中、車窓から馬見ヶ崎川河川緑地を眺望。日本一のいも煮会で有名だが、当時は暴れ川であり正之公と共に山形入りした高遠石工による治水工事で鎮まった。
次は白岩誓願寺へ。寛永15年(1638)6月、白岩郷(現寒河江市)の農民が一揆を起こした。ここは天領(石高8千石)で代官小林十郎左衛門が支配していた。その苛烈な支配に対しての一揆で、代官は之を鎮圧できず、山形城に走って正之公に助力を仰いだ。正之公は、城代家老保科民部を白岩郷に遣わし「連判状に名を連ねた者どもが目立たぬように旅宿に集まり、人数がそろったところで直訴致せ」と申し聞かせた。そうして集結した36人を捕縛し、全員を磔刑に処した。彼等と江戸で直訴した2名も加えて供養したのが「白岩義民供養塔」である。正之公の決断は独断とか違法とかと批判されることも多々あるが、中村先生は武家諸法度の再改定条項を遵守しての処罰であったと述べられた。
次に長岡山公園古戦場に向かった。明治元年9月20日の朝食中、立見尚文(鑑三郎)率いる桑名軍300は新政府軍2500に急襲されて肉薄戦となったが、立見等は長岡山に庄内藩への脱出路を見出して生き延びた。この戦いは戊辰戦役最後の戦闘であった。そこを見ようと迷っていた時、地元の方が車で臥龍橋まで先導して下さった。この戦いの戦死者の内、桑名藩18名と唐津藩1名の遺体は、陽春院の19世住職により境内に埋葬された。19体は昭和36年に発掘、確認された。私たちは戦死者の歯や、刀で斬られた頭骨や衣服、金ボタン、バックルなどを拝観した。この後、米沢市の小野川温泉「湯杜匠味庵山川」に泊り、山形牛のすき焼きに舌鼓を打った。
▼初日 東京駅発午前8時8分の東北新幹線で山形駅へ。まず山形城跡(霞城公園)。この城は慶長5年(1600)の長谷堂城の戦いの折、城郭が霞で見えなかったことが「霞城」命名の所以。保科正之公が信州高遠から栄転入部したのは寛永13年(1636)、26歳のときである。二ノ丸東大手門や旧済生館本館を見学後「香味庵まるはち」で朴葉味噌焼き御膳で昼食。昼食後寒河江市に向かい、途中、車窓から馬見ヶ崎川河川緑地を眺望。日本一のいも煮会で有名だが、当時は暴れ川であり正之公と共に山形入りした高遠石工による治水工事で鎮まった。
次は白岩誓願寺へ。寛永15年(1638)6月、白岩郷(現寒河江市)の農民が一揆を起こした。ここは天領(石高8千石)で代官小林十郎左衛門が支配していた。その苛烈な支配に対しての一揆で、代官は之を鎮圧できず、山形城に走って正之公に助力を仰いだ。正之公は、城代家老保科民部を白岩郷に遣わし「連判状に名を連ねた者どもが目立たぬように旅宿に集まり、人数がそろったところで直訴致せ」と申し聞かせた。そうして集結した36人を捕縛し、全員を磔刑に処した。彼等と江戸で直訴した2名も加えて供養したのが「白岩義民供養塔」である。正之公の決断は独断とか違法とかと批判されることも多々あるが、中村先生は武家諸法度の再改定条項を遵守しての処罰であったと述べられた。
次に長岡山公園古戦場に向かった。明治元年9月20日の朝食中、立見尚文(鑑三郎)率いる桑名軍300は新政府軍2500に急襲されて肉薄戦となったが、立見等は長岡山に庄内藩への脱出路を見出して生き延びた。この戦いは戊辰戦役最後の戦闘であった。そこを見ようと迷っていた時、地元の方が車で臥龍橋まで先導して下さった。この戦いの戦死者の内、桑名藩18名と唐津藩1名の遺体は、陽春院の19世住職により境内に埋葬された。19体は昭和36年に発掘、確認された。私たちは戦死者の歯や、刀で斬られた頭骨や衣服、金ボタン、バックルなどを拝観した。この後、米沢市の小野川温泉「湯杜匠味庵山川」に泊り、山形牛のすき焼きに舌鼓を打った。
◆二日目
二日目 先ず林泉寺に向かった。藩主上杉氏の菩提寺であり、また米沢城下町創設の恩人直江兼続夫妻の廟所として尊崇されている。境内に上杉景勝の実母仙洞院、景勝正室菊姫(信玄五女)、4代上杉綱勝正室媛姫(正之長女)、鷹山側室お豊の方の墓などや、上杉氏の奥方をはじめ武田信清(信玄六男)など上杉氏支侯の墓がある。なお上杉謙信の遺骸は米沢城本丸内の堂に安置されている。
これで山形県の史跡巡りは終り、会津若松市に入る。
まず旧滝沢本陣へ。会津戦争当時は松平容保公の出陣によって本営となり、白虎隊もここから戸ノ口原へ出陣した。建物のあちこちに弾痕や刀傷の痕跡が見られ、古文書なども展示されている。強清水の「もろはくや菅井商店」で、名物の蕎麦セットを食した。
昼食後、戸ノ口原古戦場跡に進んだ。湿地であった原っぱに「白虎隊奮戦地」の大きな碑があり、辺りに案内板や幾つかの墓碑もある。慶応4年8月22日から翌朝にかけて、白虎隊も加えた旧幕府軍が、十六橋を越えて侵攻してきた新政府軍と激戦を繰り広げた。白虎隊士は、ちりぢりになりながら鶴ヶ城を目指し、悲劇の集団自刃に至った。
十六橋は、猪苗代方面から若松城下に入るのに必要な径間16を有する石橋で、旧幕府軍は急ぎ橋の破壊を始めたが堅牢で崩すことができず撤退のやむなきに至り、会津側にとって重大な事態となったのである。現在の橋は明治13年に安積疎水事業の一環として猪苗代湖ダム化のために建設、大正3年に改築されたもの。
母成峠は戊辰戦争で重要な「母成峠の戦い」の舞台となった。新政府軍は8月21日に約3千を以て母成峠に侵攻し、ここを守備する旧幕府軍800は抵抗したが遂には敗走する。峠に「戊辰戦役母成峠古戦場」の碑と解説版、戦没者を弔う慰霊碑が建立されている。
次に二本松城を訪れた。藩兵の大半が白河口に出向いた7月26日、西軍が城下に殺到。12歳から17歳の少年兵62名も動員されて果敢に戦うも落城。数々の悲話が残された。復元された城門に、刀を背負い大砲を撃つ少年隊と傍らに我が子の陣羽織を縫う母親の像が建立されている。最後に大隣寺に参詣。本堂の裏は歴代藩主の御廟で、本堂右手に「二本松少年隊墓所」があり、小さな墓石が並んでいる。ここに線香を手向けた後、郡山駅にて解散。
(高8回 遠藤暢喜)
第13回会津歴史探訪の旅
六月三日~四日に「〝保科正之公〟生母・お静の方を庇護した松姫の足跡を訪ねる」としての旅が催行された。正之公は幼名を幸松といい、その出自から養育を託された見性院の元で育った。 見性院は武田信玄の次女で、異母妹の松姫(信玄の五女、信松尼)も幸松の養育と庇護に尽力した。
◆初日

◆二日目
午前八時、ホテルから建福寺に詣でた。元は乾福寺と称したが、正光が立藩して保科家の菩提寺に定め、寺名を建福寺と改めた。境内に正直、正光の墓碑のほか諏訪御料人(勝頼の母)の墓碑がある。その後、高遠町歴史博物館に寄った。ここでは高遠城と城下町の歴史などを聴き、敷地内に復元された絵島囲み屋敷を見学した。博物館の入り口近くに正之公とお静の石像もあり、その前で集合記念写真を撮った。絵島囲み屋敷は、正徳四年正月に起こった絵島生島事件で流刑となった絵島が幽閉され、六十一歳で没するまで過ごした屋敷である。
ここから再び勝沼に走り、大善寺と柏尾古戦場跡に行った。大善寺は養老二年に行基が薬師如来像と日光・月光菩薩像を刻して安置して開かれたと伝わる。如来像は右手に葡萄を持っていて、本寺はぶどう寺とも呼ばれる。行基がこの地の村人にブドウの作り方を教え、でブドウ栽培が広まったという。近くの柏尾橋に近藤勇像が建っている。幕末、近藤勇が率いる甲陽鎮撫隊と、板垣退助が率いる東山道先峰軍がこの辺りで激戦交わし、甲陽鎮撫隊は敗走した。また、近くのブドウ畑に会津藩士柴田八郎健吉の墓があり、大平幹事の後輩の働きで墓前まで行け、皆で線香をあげることができた。
昼食は大月駅前の松葉で摂ったが、予約の時刻より二時間強も遅れていた。大月から八王子への高速道路は大渋滞で更に遅れ、産千代稲荷神社に詣で、信松院にたどり着いたのは五時を回っていた。大平幹事は、行く先々で謝っていた。
産千代稲荷神社は、家康から八王子に置いた関東総代官所の総代官に任命された大久保石見守長安の陣屋内の鬼門の守護神として創立され、安産福徳の神として崇拝されている。長安は武田家の家臣であった。
信松院の開基は松姫(信松尼)である。天正十年に織田勢による甲州征伐が始まると、松姫は盛信の娘など四歳の姫らを伴って逃避行し、武蔵国横山宿の恩方村にたどり着いた。やがて近くの名刹心源院の和尚の仏弟子となり信松禅尼と称された。御年二十二である。天正十八年、信松禅尼は御所水の里へ移り住み庵を結んだ。現在の信松院である。松姫は織田信忠との婚約破棄後、生涯を独身で通し五十六歳で他界した。信松院の境内に松姫の墓があり、皆で焼香した。
(高8回 遠藤暢喜)